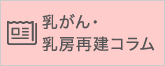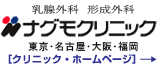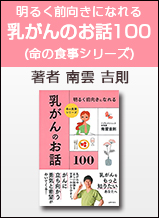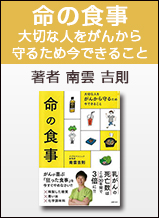乳がん・乳房再建コラム(治療からの復帰(乳がんの術後))
硬膜外麻酔
全身麻酔をする前は心電図、肺のレントゲン、呼吸機能、さらに血液検査で肝臓・腎臓の検査をしますよね。なぜこんなに検査が必要なのでしょう。
全身麻酔はのどに管を入れて麻酔ガスをポンプで送り込みます。この間、呼吸は止まった状態で、麻酔医が目を離したすきに事故でも起きたら命にかかわります。また麻酔ガスは肝臓や腎臓に負担がかかるのです。ですから心臓病や喘息、肝臓・腎臓の病気があるときや、老人、全身衰弱の人、妊婦は全身麻酔をかけられません。そこでこの硬膜外麻酔を使用します。
背中から麻酔するというと、よく「脊髄麻酔」と勘違いされます。脊髄麻酔は盲腸のときに行われる中枢麻酔で、脊髄神経をブロックします。そのためブロックしたところから下は筋肉も麻痺して動けなくなります。脊髄は脳とつながっているので、麻酔薬が脳のほうに流れれば呼吸も止まってしまいます。
硬膜外麻酔は背中から1mmぐらいの太さの管を入れて、胸の知覚神経である肋間神経をブロックする、いわば局所麻酔の一種です。無痛分娩に使われたり、四十肩の治療にペインクリニックの外来で行われたりします。
硬膜外麻酔と同時に安定剤を使いますので手術中はグーグー寝ていますし、手術が終わったらベッドまで歩いて帰れます。全身麻酔よりも安全で、身体に負担がないので、日帰り手術にも適しています。入院の場合は、次の日まで局所麻酔薬を少しずつ流していますので、術後の痛みを取ってくれます。
以前、ほかの病院で同時再建を2件頼まれたとき、1人は全身麻酔だけだったので、麻酔が覚めたあとは一晩中痛かったそうです。もう1人は硬膜外麻酔が入っていたので術後も痛みがなく大変元気でした。困ったのは2人が友人同士だったので、どうして自分は硬膜外麻酔が入っていなかったのかと主治医が責められたそうです。
最近は、ちょっと進んだ病院では、乳がんや肺がんなどの胸の手術のときは、この硬膜外麻酔を併用しています。手術の前に主治医に確認してください。
セレモニー
昔の家にはネズミがすみ着いていたものです。みんなで食卓を囲んでいると、ネコが何かを得意げにくわえてくる。何かと思ったらネズミです。今だったら「そんな不潔なもの持ってこないでちょうだい!」といって金切り声を上げるでしょうが、昔は家族全員でほめてあげたものです。ネコはほめてもらいたくて見せびらかしに来たのです。
手術が終わると、家族が手術室に呼び出されて、執刀医(手術をした医師)の説明を受けます。医師は金属製の膿盆(空豆の形をした大きなお盆)にのせた血だらけのものをプリンのようにゆらゆらさせながら運んできて、「この部分ががんです、がんは取り切れました、リンパ節にも転移はありませんでした」といいます。
私はこれを「セレモニー」と呼んでいます。ネコがネズミを見せびらかしているのと同じような儀式だからです。
「これががんです」といったって、乳がんは脂肪に包まれているので直接は見えません。
切り目を入れて中を見せようとする医師もいますが、病理の診断が難しくなります。
「がんが取り切れたかどうか」、それを調べるのが病理医の仕事です。
サッカーや野球でいえばわれわれ外科医はプレーヤー(選手)、最善のプレーをするのが仕事。それがアウトかセーフかを決めるのはレフリー(審判)である病理医の仕事です。
ですから手術が終わった時点では、「手術は無事終わりました。ご安心ください。結果は外来でお知らせします」としか申し上げることはありません。そのかわり、病理結果が出たらそのコピーを差し上げます。外科医のいいかげんな説明よりも、病理医の詳しい診断結果を待ちましょう。
そして病理結果のコピーは必ずもらいましょう。これさえあれば術後の治療法を決めるとき他の医師の意見も聞けるからです。
結果が出るまではあまり気をもまずに英気を養ってください。
麻酔から覚めたら
乳がん手術を受けることはあなたにとって初めての連続で、いくら用意を周到にしたつもりでもとまどうことばかりでしょう。思ったとおり大変だったという方もいれば、予想したよりも楽だったという方もいます。そこで手術直後の麻酔が覚めた状態から、術後の回復、そして退院、社会復帰に至るまでを事前に知っておきましょう。
目が覚めたらあなたはリカバリー(回復室)のベッド上にいます。麻酔から完全に覚めて出血のおそれがなくなるまでは、食事を摂ることもトイレに歩くこともできません。
- 意識
- 手術後、数時間は全身麻酔の影響でもうろうとした感じがします。
- 呼吸
- 全身麻酔ではのどにチューブを挿入するため、のどの痛みを感じることもあります。のどの入り口までしか管を入れない「ラリンジアルマスク」なら痛みは少ないでしょう。呼吸を補助するために酸素マスク(または鼻に酸素チューブ)が装着されています。あなたの指先に洗濯ばさみのようなものがついていますが、血液中の酸素濃度を測っています。異常があれば看護師が飛んできてくれます。
- 心電図
- あなたの胸部にはってあるシールは、あなたの心電図を看護室(ナースステーション)から看視するためのものです。けっしてはずしてはいけません。
- 静脈留置針
- 腕には水分、栄養、薬剤を投与する目的で点滴用の管がついています。これは食事が摂れるようになるまでのいわば命網です。食事が十分に摂れるようになった時点で抜去します。
- 尿道カテーテル
- 膀胱には尿を体外に出す管が挿入されているため、常に尿をしたいような不快感があるでしょう。しかし勝手に抜いてはいけません。あなたの腎臓が正常に働いているか、点滴量が十分かを判断するために、尿量を量る必要があるのです。
- 傷
- 傷はガーゼでおおわれており、ドレーン(滲出液を排出するためのチューブ)が脇の下と傷口に挿入されています。
- ナースコール
- 痛みはがまんしてはいけません。呼吸が浅くなり術後の合併症が増すとともに、体力を消耗し回復が遅れるからです。吐いたものがのどに詰まることも危険です。痛いとき苦しいときには看護師を呼びましょう。あなたが握っているナースコール(ブザー)を押してください。
4つの自立とは?
日本では、交通事故で手や足を骨折したとき、骨がくっつくまで3カ月も入院させます。身体は元気なわけですから、看護師をからかったり、待合室でタバコを吸いながら将棋をしたりして3カ月を過ごすわけです。
これがアメリカでしたら骨折した日にギプスをして、翌日から仕事場に出て電話番をするのです。しなければクビです。
また日本では出産すると1週間入院して何十万円も払うのですが、欧米では1日入院、アジアやアフリカでは入院すらしません。
乳がんの手術直後はどこの病院でも、点滴をして、おしっこの管を入れて、傷にはドレーンという滲出液を抜く管が入っていますから絶対安静です。しかし翌日になれば自分で歩けて(自立歩行)、自分で排便ができて(自立排泄)、自分で食べられて(自立摂食)、痛み止めの点滴が必要なくなります(痛みからの自立)。これを「4つの自立」といいます。
もう点滴もおしっこの管もいりません。自分で歩いて食事を取りに行って、自分で食べて、自分であと片づけをして、自分でトイレに行けるのです。
友達が見舞いに来ると、この入院のためにわざわざ買い求めたパジャマの上に、これまた新調したガウンを着て、「今日はもう3回目よ」といいながら下の喫茶店に行くのです。はたして入院している必要がどこにあるのでしょう?
確かにリンパ節を全部取るとリンパ液が止まらなくなるので、ドレーンがなかなか抜けません。しかし最近はセンチネルリンパ節生検といってリンパ節を少ししか取らないので、ドレーンは翌日には抜けます。
ですので、アメリカでは乳がん手術の80%が日帰りで行われています。手術といえば長期入院が当たり前のわが国では信じられない方も多いと思いますが、実は先進国ではデイサージャリー(day surgery)呼ばれ、長い歴史があるのです。
「日帰り手術」と翻訳されていますが、その定義は「23時間以内の退院」をさすため、正確にはデイサージャリーは「日帰り・一泊手術」となるでしょう。
デイサージャリーの重要性
アメリカで入院期間が短い最大の理由は院内感染の予防です。
昔、アメリカのある大病院で院内感染が大流行しました。MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)という抗生物質の効かない怖い菌です。同じ入院室にこの菌をもっている人がいれば、1週間以内に部屋中の人に感染します。ミツバチが花粉を運ぶように医師や看護師がこの菌を運んでいるのです。
まず、この病院では入院患者全員にMRSAに効く抗生物質を点滴しました。ところがすぐに耐性菌が出て、その抗生物質も効かなくなりました。
次に、病院中を消毒しまくりました。しかしこれも効果がありませんでした。
そこで、入院患者のうち、4つの自立状態にある人を自宅に帰したり、近くのモーテルに移したりしました。これが功を奏してMRSAを鎮圧できたのです。
病院は病人のいるところです、そこに長期入院をすることは病気をもらうようなものです。早期退院は術後感染症を防ぐための妙薬なのです。
そのほかにも長期入院は患者さんにさまざまな「肉体的、精神的、時間的、経済的」負担を与えていることを忘れてはいけません。
- 肉体的負担
- 合併症が増加します。院内感染は肺炎のウイルスのこともあります。また長期間の寝たきりは肺炎、心不全、運動機能の低下、認知症の原因となります。
- 精神的負担
- あなたは夫や子ども、そして会社やペットにとってなくてはならない人です。長期入院することは彼らにとって大きな負担となります。そのことがあなたにも精神的負担となります。
- 時間的負担
- 本来、医療は早期社会復帰を目的としているはずなのに、入院が長引くほど社会復帰が困難になります。
- 経済的負担
- 入院費を含む医療費の負担が増加します。また仕事を休んだり辞めたりしたことの経済的負担はかなりのものです。
考えてみてください。外科生検(しこりのくりぬき検査)もリンパ節生検も通常は通院で行われています。なのに、それらを同時にやる乳房温存術でなぜ何週間も入院させられるのでしょう?本当は通院で十分なのです。
クリニカルパス
学生のころは地図もガイドブックもなく、ふらりとひとり旅に出ました。見知らぬ土地で見知らぬ人とのふれあいを期待して。実際はなんの出会いもふれあいもなく、途方に暮れたことがほとんどでしたが、つらいと思ったことはありませんでした。
最近は外国に行くときも招待講演がほとんどですので、切符もホテルも相手が手配してくれて、空港に迎えが来ています。しかし先日、なんの手違いか空港で迎えが見つからず、自分でホテルまで移動しなければならなかったのです。ガイドブックもなく予備知識もなかったため、周りのすべてが悪い人に見えて泣きそうでした。
さて手術直後の経過も、私たちにとっては日常茶飯事ですが、あなたにとっては何をされるのか戦々恐々です。せめてガイドブックでもあるなら、と思うでしょう。実はあるのです。それはクリニカルパス、臨床の行程表という意味です。早期の離床(ベッドから離れること)をめざして、次のような情報を提供してくれます。
- 意識状態を調べ、麻酔から覚めていることを確認します。
- 血圧や体温を測ります。
- 採血をして貧血が生じていないことを確認します。
- 創部に血がたまっていないか確認します。
- 電動ベッドの頭部を徐々に上げていきます。
- 少しずつ飲水を開始します。
- 尿道カテーテルを抜いてトイレ歩行をします(歩いてみてから管を抜くこともあります)。
- 点滴の針や硬膜外麻酔の管を抜きます。
途中で吐き気や気分不快が生じたときは、すぐにベッド上安静とし最初からやり直します。この回復プログラムは、一泊以上の入院のときは翌朝から、日帰り手術のときは術後数時間後から始めます。
家に帰ってから注意すること
病院は居心地の悪いところです。もし居心地がよくても、それはあなたのいるべき場所ではありません。入院期間が長ければ社会復帰にはその倍の時間がかかると思ってください。可能であるのなら退院して家に帰り、あせらず恐れず一歩ずつ社会復帰していきましょう。家に帰ったら次のようなことをします。
- 帰った日はのんびりしよう
- とはいえ、布団に寝てしまっては起きるのが一苦労です。ソファでごろごろして、留守中に届いた手紙(ほとんどがダイレクトメールでしょうが)や、書類(これもガスや電気の請求書がほとんどですが)に目を通しましょう。
- 入浴しよう
- わが国では抜糸が終わるまで入裕させないことが多いのですが、傷の治りを考えればナンセンスです。昔から「湯治」といいます。入浴したほうが傷の治りがいいのです。ドレーンが抜けたらその翌日からシャワーが可能です。傷口から滲出液が出なくなったら肩まで入浴しましょう。
- 身の回りのことを自分でしよう
- 日常生活に戻るための機能訓練をリハビリといいます。運動機能に関する後遺症がないかぎり、病院でリハビリを受ける必要はありません。自分の身の回りのことを自分でする、それがリハビリです。
- 外に出てみよう
- 今までなんでもなかったことがとてもおっくうになったり不安に感じたりします。混雑した電車に乗ることや買い物に行くこともそのひとつです。不安なときは家族や友人につきそってもらって外出してみましょう。
- 仕事に復帰しよう
- このご時世です。一度クビになったらなかなかいい仕事は見つかりません。もしあなたが仕事に生きがいを感じるならば、周囲の人に協力を求めながら仕事に復帰しましょう。
- スポーツや旅行を楽しもう
- 自分の身の回りのこともできないのに、いきなりスポーツや旅行をすることはできません。しかし、主治医の許可が出たら恐れずトライしてみましょう。きっと気分転換になるはずです。
- 夫や恋人との愛を深めよう
- 出産や病気を機に夫との性生活は疎遠になります。相手はあなたにふれてはいけないと思っているのです。あなたがふれられても痛くなくなったら、きっかけをつくってあげてください。

 はじめに
はじめに